オンラインでふれる社会学 - 北樹出版の大学教科書
オンラインでふれる社会学
『ふれる社会学』で取りあげられなかったことに「ふれる」
■第9章「レインボーにふれる」関連お役立ちWeb集
「包帯のような嘘」
- ライター/YouTuberであるマサキチトセさんの個人サイト。
ジェンダー・セクシュアリティに関連する問題に鋭く切り込むコラム記事が掲載されているほか、クィア英会話講座のYouTube動画もアップされている。
「delta-G」
- ミヤマアキラさんによる、ノン・ヘテロ(同性愛者等)のブログであり、ニュースコンテンツサイト。
中でも「クィア・スタディーズ入門」のカテゴリーには、清水晶子さんが講師を務めた「クィア・スタディーズ講座」のレポートもあり、クィアという概念に初めてふれる人は必読である。
「おきく's第3波フェミニズム」
- ジェンダー・セクシュアリティを中心に社会学的に研究している菊地夏野さんのブログ。
ブログタイトルにもなっている第三波フェミニズムはもちろんのこと、クィア/LGBT 、セックス・ワーク、日本軍「慰安婦」問題、原発/震災など、幅広いテーマを扱った記事が投稿されている。
「Feminism and Lesbian Art working group」
- レズビアン・アーティストのネットワーキングとアートにおける異性愛主義についての批評分析をすることを目的に活動を始めた、「フェミニズムとレズビアン・アートの会」のブログ。
現在は、プロジェクト「フツーのLGBTをクィアする」の活動が活発である。ピンクウォッシング(イスラエルが、LGBTの権利を擁護しているとアピールすることによって、あたかも人権を尊重している国であるかのようなイメージを作り出し、パレスチナ攻撃・占領を通してパレスチナ人の人権侵害をしていることを隠蔽しようとする外交政策)への抗議の呼びかけを行っていたり、フェミニズムとクィアと障害にまつわる読書会を開催していたりする。最新情報は「フツーのLGBTをクィアする」Twitter(https://twitter.com/lgbtq_luna)にて。
「#あたシモ」
- 「アメリカで働くレズ」であるイチカワユウさんによる、世界のLGBTQ情報を中心に扱ったブログ。
特にエンターテイメントとクィアにまつわるレビュー記事が充実している。
Twitter(https://twitter.com/yu_ichikawa)でも積極的に情報発信されている。
■第11章「ハーフにふれる」・拡張版!
「ハーフにふれる」章をお読みくださり、ありがとうございます。本ページでは、さらに議論を拡張するための手がかりをご紹介示していきたいと思います。
◇まず、「ハーフ」や外国に(も)ルーツをもつ人々の日常にフォーカスしたwebサイトと本の「組み合わせ」のご案内です。
HAFU TALK(ハーフトーク)
- なお、共同代表のうち、ケイン樹里安と下地ローレンス吉孝は『現代思想』2019年4月号「新移民時代」特集にそれぞれ論考が掲載されています。
私のエッジから観ている風景
- HAFU TALKにもゲストコラムを執筆されている金村詩恩さんのブログ。
- 同名のタイトルをもつ書籍、『私のエッジから観ている風景—日本籍で、在日コリアンで』と共にご覧ください。
温聲提示
- 『「国語」から旅立って』『空港時光』の著者である温又柔さんのお知らせブログ。
「国語」という何気なく見聞きしてきた言葉の、「なぞ」に迫りたくなるはず。
◇お次は、「ハーフにふれる」章とほかの章との接続地点を!
金南さんが手がけた「外国につながる子どもにふれる章」との接続。
栢木さんが手がけた「差別感情にふれる」章との接続。
稲津さんが手がけた「魂にふれる」章との接続。
- 「魂」の序列化のなかで言及した差別と排除に関する学びを深めたい人には、『差別と排除の社会学』という書籍があります。栢木さんが執筆された差別感情の自己点検という論点とも重なる議論がなされています。→こちら
- 本章の発想の元になった論文が所収されている『社会的分断を越境する』という書籍があります。この書籍には栢木さんにもご寄稿頂きましたし、ケインさんには書評者という形でお世話になりました。(稲津)→こちら
- 本文中に紹介した「1.17のつどい」が始まるときの街の様子については、神戸新聞社による「阪神・淡路大震災24年」のカメラ中継映像があります。(稲津) → こちら
喜多さんが手がけた「身体にふれる」章との接続。
- 喜多さんが示した「理想の身体」と「ハーフ顔」の問題を結ぶ議論としては、渡会さんの論文がオススメです。「メスティサ」から「ハーフ」へ : 日本への国際移動と日系ブラジル人女性の人種化
◇そして、絶対に取り上げねばならない問題状況としての「入管」! 入国管理局で、なにが行われているのか。東京オリンピック招致活動で「お・も・て・な・し」と滝川クリステルさんに言わせておきながら、そして、移民とは呼ばずに「外国人材」とヒトをモノのように呼ぶこの社会で、多くの人々を信じられないほど過酷な状況で拘束する、人為的な仕組み。いつ変えるの?いまでしょ?ほんまに。
「わたしが入管をやめたワケ」
- 問題状況を知るための手がかりをえるために『移民政策とはなにか』もぜひ。
どしどし更新していく予定です!また、ぼちぼち見に来てください!
再び、このページに「ふれる」ときをお待ちしております。(ケイン樹里安)
■第15章「100年前の社会学にふれる」から、ほかの社会学の教科書/入門書にふれる
本コラムでは、社会学および社会調査の方法をさらに学ぶためのガイドラインとして、いい意味での「定番」やエッジの効いたおススメ本を紹介します。以下の見出しをクリック!(随時更新予定)
社会学の教科書/入門書
- 命題コレクション・社会学(作田啓一・井上俊編,1986,筑摩書房)
- 社会学ベーシックス(井上俊・伊藤公雄編,2008~2011,世界思想社)
- 社会学 第5版(アンソニー・ギデンズ,2009,而立書房)
- 社会学の名著30(竹内洋,2008,筑摩書房)
- 社会学 (New Liberal Arts Selection)(2019,長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志,有斐閣)
- 社会学への招待(ピーター・L・バーガー,2017,筑摩書房)
- 社会理論と社会構造(ロバート・L・マートン,1961,みすず書房)
- リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待 ブルデュー、社会学を語る(ピエール・ブルデュー&ロイック・J・D・ヴァカン,2007,藤原書店)
- ジンメル・コレクション(ゲオルク・ジンメル,1999,筑摩書房)
- 社会学入門―社会とのかかわり方(筒井淳也・前田泰樹,2017,有斐閣ストゥディア)
and more…
社会調査
- よくわかる質的社会調査 技法編(谷富夫・芦田徹郎編,2009,ミネルヴァ書房)
- よくわかる質的社会調査 プロセス編(谷富夫・山本努編,2009,ミネルヴァ書房)
- 質的社会調査の方法 他者の合理性の理解社会学(岸政彦・石岡丈昇・丸山里美,2016,有斐閣ストゥディア)
- 最強の社会調査入門 これから質的調査をはじめる人のために(前田拓也・秋谷直矩・朴 沙羅・木下衆,2016,ナカニシヤ出版)
- 基礎社会学 新訂第4版(酒井千絵・永井良和・間淵領吾,2018,世界思想社)
- 私がアルビノについて調べ考えて書いた本 当事者から始める社会学(矢吹康夫,2017,生活書院)
- はじめての参与観察 現場と私をつなぐ社会学(山北輝裕,2011,ナカニシヤ出版)
- インタビューの社会学 ライフストーリーの聞き方(桜井厚,2002,せりか書房)
- ライフストーリー研究に何ができるか 対話的構築主義の批判的継承(桜井厚・石川良子 編,2015,新曜社)
and more…
「論文の書き方」指南書リスト
「コトハジメるコツ!4 卒論へと筆をとる」では、文字通り「筆をとる」ための心得を示すに留め、具体的な「卒論の書き方」については触れていません。ここでは、具体的な論文の書き方に悩む人たちに参考になりそうな指南書をリストにしてみました。これらは、わたし(菊池)が実際に読んだものであり、特に1と2は実際の卒論指導でも学生に紹介しているものです。ご自身に必要だと思われるものを選んで読んでいただけるとよいと思います。
また、3は指南書としてだけでなく、人文書としても興味深く読むことができるものです。これらもぜひ手に取ってみてください。
4と5は研究者のタマゴやすでに孵化した方々にもオススメです。「目から鱗」の記述に出会うことでしょう。
注1:どれもオススメできて序列が付けられないので著者姓アルファベット順になっています。
注2:品切れ等で流通していないものも含んでいます。その場合は、図書館、古書店等で探してみてください。
以下の見出しをクリック!
1.「どう書けば論文になるの?」という人はまずここから
1補. 「伝わる文章」を書くためにも読んでおきたい
2.もう一歩前進するために読みたい
- 石原千明,『大学生の論文執筆法』(筑摩書房(ちくま新書), 2006年).
- 鹿島茂,『勝つための論文の書き方』(文藝春秋(文春新書), 2003年).
- 木下是雄,『レポートの組み立て方』(筑摩書房(ちくま学芸文庫), 1994年).
- 小笠原喜康,『最新版 大学生のためのレポート・論文術』(講談社(講談社現代新書), 2018年).
- 澤田昭夫,『論文の書き方』(講談社(講談社学術文庫), 1977年).
- 澤田昭夫,『論文のまとめ方:わかりやすいまとめ方』(講談社(講談社学術文庫), 1983年).
- 白井利明・髙橋一郎,『よくわかる卒論の書き方 [第2版]』(ミネルヴァ書房, 2013年).
- 戸田山和久,『新版 論文の教室:レポートから卒論まで』(NHK出版(NHKブックス), 2012年).
- 都築学,『大学一年生のための 伝わるレポートの書き方』(有斐閣, 2016年).
- 上野千鶴子,『情報生産者になる』(筑摩書房(ちくま新書), 2018年).
- 鷲田小彌太,『入門・論文の書き方』(PHP研究所(PHP出版), 1999年).
3.論文を書くのに役に立つ「考え方」も学ぶ
- 千葉雅也,『勉強の哲学:来たるべきバカのために』(文藝春秋, 2017年).
- 読書猿,『アイデア大全:想像力とブレイクスルーを生み出す42のツール』(フォレスト出版, 2017年).
- 藤田真文(編著),『メディアの卒論:テーマ・方法・実際 [第2版]』(ミネルヴァ書房, 2016年).
- 福田和也,『[改訂版] ひと月百冊読み、三百枚書く私の方法』(PHP研究所(PHPビジネス新書), 2014年).
- 板坂元,『考える技術・書く技術』(講談社(講談社現代新書), 1973年).
- 川喜多二郎,『発想法:創造性開発のために 改版』(中央公論新社(中公新書), 2017年).
- 清水幾太郎,『論文の書き方』(岩波書店(岩波新書), 1959年).
- 高根正昭,『創造の方法学』(講談社(講談社現代新書), 1979年).
- 鶴見俊輔,『文章心得帖』(筑摩書房(ちくま学芸文庫), 2013年).
- 梅棹忠夫,『知的生産の技術』(岩波書店(岩波新書), 1969年).
4.さらに先を目指すなら読みたい
5.いろいろな人の論文執筆法に触れてみたい人は
ふれしゃかフェス(『ふれる社会学』トークイベント)アーカイブ
第1〜5回まではレポートをご覧いただけます。(登壇者名敬称略)
第1回「社会を紡ぎ直すために」
ケイン樹里安×上原健太郎×辻泉 2019.11.8(金)@代官山蔦屋書店
第2回「生きづらさにふれる」
ケイン樹里安×上原健太郎×栢木清吾×中村香住 2019.11.9(土)@ジュンク堂池袋店
第3回「境界にふれる」
ケイン樹里安×上原健太郎×八木寛之×栢木清吾×福嶋聡 2019.11.16(土)@ジュンク堂難波店
第4回「社会学にふれて、さらに読む、そして書く」
ケイン樹里安×上原健太郎×菊池哲彦×中村香住 2019.12.7(土)@Readin’Writin’ BOOK STORE
第5回「『ふれる社会学』×『よい移民』刊行記念:差別のカジュアルさにふれる」
栢木清吾×稲津秀樹×ケイン樹里安 2019.12.14(土)@汽水空港
第6回「岸政彦にふれる」
岸政彦×ケイン樹里安×上原健太郎 2020.1.13(月・祝)@Loft PlusOne West
第7回「『ふれない社会』にふれる」
ケイン樹里安×上原健太郎×栢木清吾×稲津秀樹×有國明弘×ヒトミ・クバーナ×桑畑洋一郎×小林さやか 2020.5.31(日)@Loft PlusOne West(オンライン)
第8回 「ダイバーシティにふれる」
マサキチトセ×ケイン樹里安×上原健太郎×中村香住 2020.7.5(土)@足湯cafe&barどん浴(オンライン)
ふれしゃかフェス情報は北樹出版Twitter、Facebookにて更新中です!
→Twitter
→Facebook
執筆者紹介(初版第1刷2019年11月刊行時)
 |
| ||||
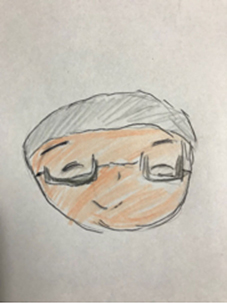 |
| ||||
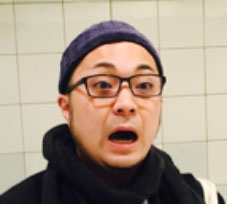 |
| ||||
 |
| ||||
 |
| ||||
 |
| ||||
 |
| ||||
 |
| ||||
 |
| ||||
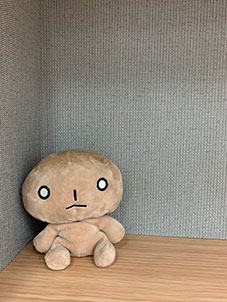 |
| ||||
 |
| ||||
 |
|

